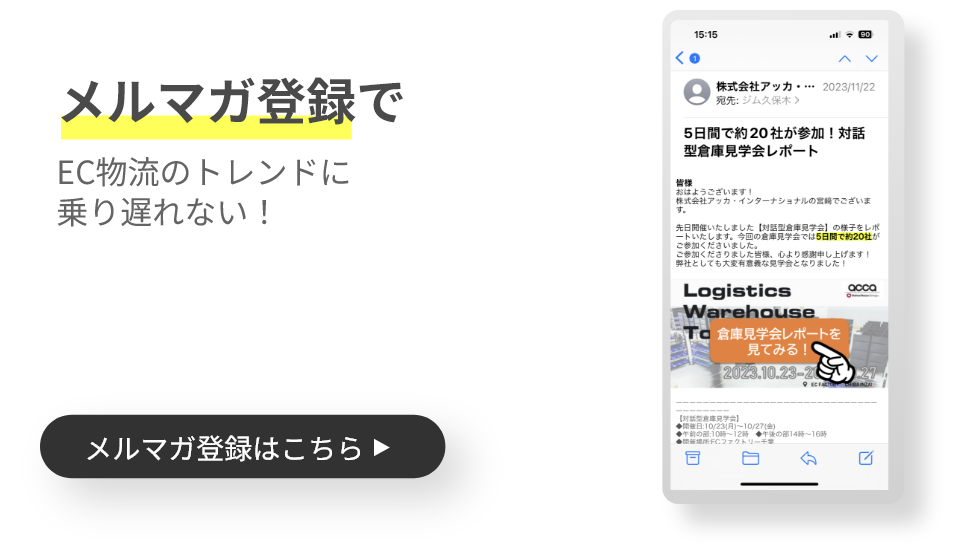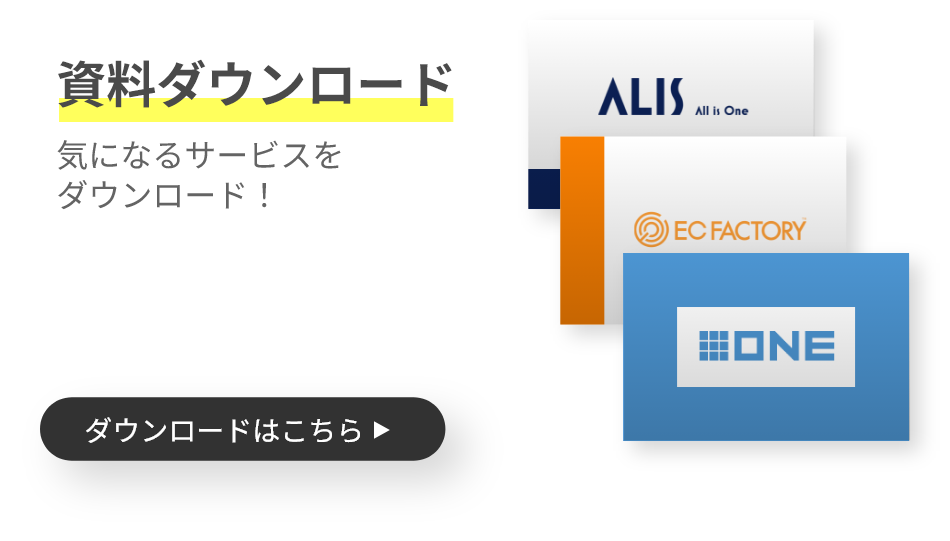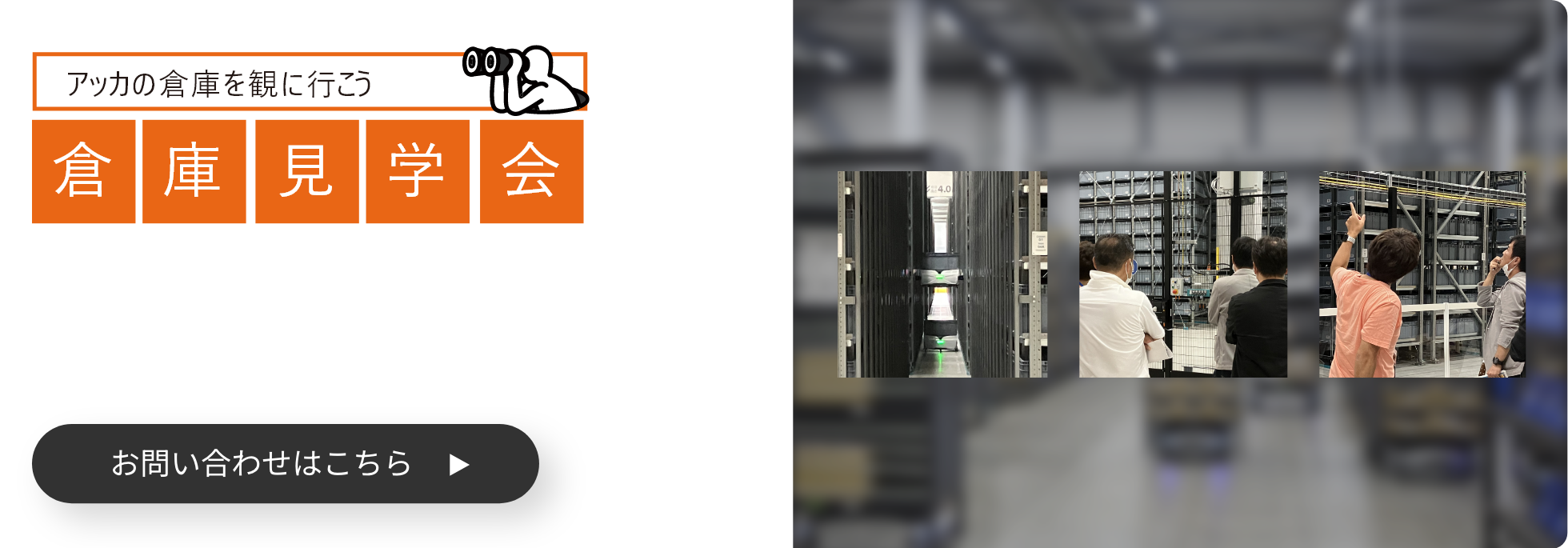「物流の2024年問題」は、厚生労働省が働き方改革によってトラックドライバーの残業時間上限規制という「火事」を起こし、それを経済産業省・国土交通省・農林水産省の3省が物流革新という旗の下、「火消し」にあたるというマッチポンプです。
なぜ、政府は「物流の2024年問題」というマッチポンプを仕掛けてまで、物流革新を行おうとしているのでしょうか?
実は、この理由を知ることで、あなたの新物効法に対する向き合い方が変わるかもしれません。
物流革新政策の肝である物流総合効率化法改正のポイントを紐解きつつ、考えていきましょう。
物流総合効率化法とトラック法
2024年5月、今後の物流政策の中軸となるふたつの法律が公布されました。
- 物流総合効率化法(略称は、「物効法」)
(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から、「物資の流通の効率化に関する法律」に改称) - 貨物自動車運送事業法(略称は、「貨物事業法」あるいは「トラック法」)
物流総合効率化法は、荷主および物流事業者に対し、物流効率化に対する取り組みを定めた内容。
トラック法は、トラック事業者の事業遂行における取り組みを定めた内容となっています。
物流総合効率化法および新トラック法に先んじること1年、政府は以下の指針を発表しています。
- 「物流革新に向けた政策パッケージ」(2023年6月2日)
- 「物流革新緊急パッケージ」(2023年10月6日)
このふたつの指針で、政府は物流革新政策の概要を示しました。物流総合効率化法と新トラック法もそのひとつです。
そして、新物流総合効率化法は2024年9月に、新トラック法は2024年11月に、それぞれパブリックコメント募集が行われました。
物流総合効率化法については、2024年11月11日、「第4回 交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会・食料産業部会 物流小委員会 合同会議」(以下、合同会議)で、パブリックコメントの結果を踏まえた取りまとめが議論され、いよいよその全容が詳(つまび)らかになろうとしています。
物流総合効率化法のポイント
物流総合効率化法について、話題となっているポイントは、概ね以下の3つです。
- 特定事業者の義務と基準
- 特定荷主らに課されるCLO選任義務化
- 荷待ち・荷役時間の2時間以内ルール(1運行2時間以内ルール)
特定事業者の義務と基準
貨物自動車運送事業者(運送会社)、荷主、倉庫業者、連鎖化事業者(フランチャイズチェーン本部)のうち、定められた基準を超える事業者は、特定事業者に指定されます。
それぞれの基準は以下のとおりです。
- 特定荷主・特定連鎖化事業者
- 年間取扱貨物重量 9万トン以上の事業者が対象
- およそ半数の荷主(上位3,200社程度)
- 特定貨物自動車運送事業者
- 保有車両台数 150台以上の事業者が対象
- 国内トラック輸送能力のおよそ半分をカバーするように設定(上位790社程度)
- 特定倉庫事業者
- 年間入庫貨物重量 70万トン以上の事業者が対象
- 国内貨物保管能力のおよそ半分をカバーするように設定(上位70社程度)
特定事業者は、物流効率化を実現するための中長期的な計画の作成、その進捗状況に対する定期報告などが義務付けられ、その取り組みが不十分だと判断された場合、国から勧告・命令が行われます。
ちなみに、特定事業者ではない荷主、物流事業者の場合、物流効率化は努力義務とされています。
つまり特定事業者に指定されると、大きな責任と負担が生じることになります。
特定荷主らに課されるCLO選任義務化
特定荷主、特定連鎖化事業者は、CLOを選任しなければなりません。
CLOとは、「Chief Logistics Officer」の頭文字を取ったもので、「物流統括管理者」と訳されます。
これまで政府が発表してきた資料では、「物流”管理”統括者」(※"管理”と"統括”の順番が違います)という名称や、あるいは「CLO=物流統括管理者」であると明言してこなかったことから、CLOについてはさまざまな見解が生じていました。
しかし、合同会議では「CLO=物流統括管理者」と明言しています。
この点については、筆者も直接、経済産業省に問い合わせましたが、間違いないとのことでした。
新物流総合効率化法におけるCLOは、物流効率化に向けた取り組みにおける全責任を負い、また物流効率化のための中長期的な計画を作成・報告を行わなければなりません。
したがって、CLOとしての職務を果たすためには、企業内における高く広範な権限が必要となるため、「その立場としては、基本として、重要な経営判断を行う役員等の経営幹部から選任されることが必要である」(※合同会議資料より)とされています。
荷待ち・荷役時間の2時間以内ルール(1運行2時間以内ルール)
本件は、「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」(2023年6月2日、国土交通省)において登場し、巷では「荷待ち・荷役等時間の2時間以内ルール」などと呼ばれてきましたが、合同会議資料では「1運行2時間以内ルール」と分かりやすく端的な呼称が当てられています。
名称のとおり、1運行2時間以内ルールでは、運転以外の付帯業務の総時間を、1運行あたり2時間以内に収めることが求められます。
ここでいう付帯業務について、合同会議資料では代表的な具体例として以下を挙げています。
- 荷役
- 検品
- 荷造り
- 入庫・出庫
- 棚入れ・棚出し
- 仕分け
- 商品陳列
- ラベル貼り
- 代金の取立て・立替え
ちなみに、1運行2時間以内ルールでは、荷待ち・荷役等の時間(付帯業務に要する時間)を1時間以内に収めることを目標としています。
つまり、「2時間以内」というのは目標ではなく義務であり、2時間を超える荷待ち・荷役時間を発生させている荷主や物流センター等は、トラック・物流Gメンや公正取引委員会に摘発され、最悪のケースだと、改善勧告・改善命令を受けてしまう可能性もあります。
さらに言うと、特定事業者に指定されていない企業においても、1運行2時間以内ルールを守らない場合は、トラック・物流Gメンから働きかけ、要請、勧告・公表といった処分を受けたり、あるいは(今年公布予定の改正下請法が前提にはなりますが)公正取引委員会から「優越的な地位の濫用」とみなされる可能性が、より高まることが考えられます。
新物流総合効率化法のスケジュール
本稿で取り上げたような詳細な取り決めは、今後2回に分けて、政令・省令で施行され、あるいは告示が行われる予定です。
- 2025年4月に施行予定の内容
- 基本方針
- 荷主・物流事業者等の努力義務・判断基準
- 判断基準に関する調査・公表 等
- 2026年4月に施行予定の内容
- 特定事業者の指定
- 中長期的な計画の提出と定期報告
- CLOの選任 等
ちなみに、特定事業者に該当する企業に対しては、政府から通知されるそうです。
でも、「年間取扱貨物重量 9万トン」という基準値を超えているかどうかを、当事者ではない政府がどうやって把握するのでしょうね?
このあたりは、実行方法・実現方法に疑問が残ります。
実際のところ、まだ物流総合効率化法が効力を発揮するスキームを作り上げるためには、まだあやふやな部分や、これから詰めていかなければいけない部分が多数あるということでしょう。
なぜ、政府は「物流の2024年問題」というマッチポンプを仕掛けたのか?
おそらく、新物流総合効率化法に対して、「なんだか新たな義務(CLO選任や1運行2時間以内ルールなど)が課されて、負担が増える厄介な法律だなぁ...」という印象を抱いている企業も少なくないのではないでしょうか。
それゆえに、現状では「とりあえず詳細な情報が判明するまで、何もせず様子見をしておこう」という企業もあります。
一方で、さまざまな取り組みを行い、新物流総合効率化法における義務はもちろん、それ以上の物流革新を、既に実現しつつある企業も、荷主、物流事業者問わず、登場し始めています。
この差を生む要因って、どこにあるのでしょうね?
筆者は、「物流の2024年問題」の本質を理解しているかどうか、その違いが、物流革新に対するスタンスの違いを生んでいると考えています。
2024年7月25日に政府が開催した「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」において、岸田総理大臣(当時)が、とても興味深い発言を行っています。
「物流は、国民生活や経済を支える重要な社会インフラです。今後の人口減少社会を見据えると、物流機能維持には、既存の物流インフラを活用しつつ、物流の常識を根本から革新していく取組が不可欠です」(岸田総理大臣)
これこそが、政府が「物流の2024年問題」というマッチポイントを仕掛けてまで、物流革新を成し遂げようとしている理由です。
少子高齢化によって、超高齢化社会に向かおうとしている日本では、人海戦術によらず、より高い生産性を実現する賢い働き方が求められています。これは、物流業界に限った話ではないのですが。
だからこそ、岸田首相は、「物流の常識を根本から革新していく取組が不可欠」と発言しているわけです。
そして、このことを理解している荷主や物流事業者は、新物流総合効率化法という法的強制力が発動する前に、競合他社との競争力を高め、自社のビジネスをより強固にするために、既に「今までの物流のやり方」を自ら疑い、改善・変革を行う物流革新に着手しているわけです。
新物流総合効率化法、あるいは新トラック法も同様なのですが、法律とは、「とりあえずこれ(※法律内の義務等)だけやっておけば、社会課題の解決に向けた最低限の必要条件はクリアできる」というもの。
そのように考えると、物流総合効率化法とは、政府が企業の物流業務について、進化すべき方向性、ビジネスチャンスの方向性を指し示したものとも言えます。
「物流総合効率化法の改正かぁ、面倒くさいなぁ...」と考えるのではなく、自社ビジネスのよりよい発展を目指すため、新物流総合効率化法を物流強化を果たすための参考書として、活用してくれる企業が増えてほしいものです。